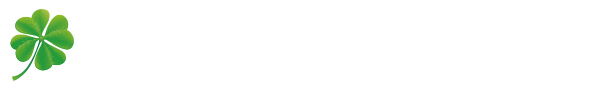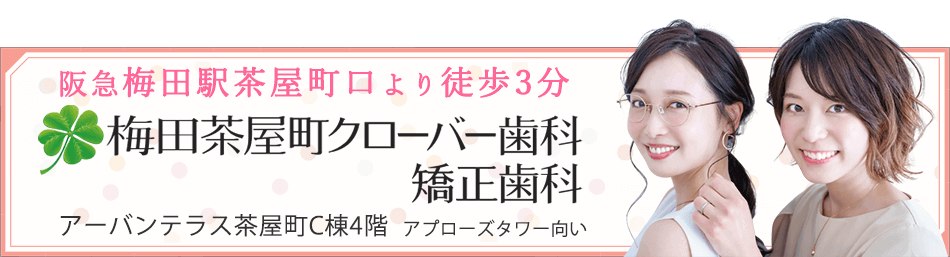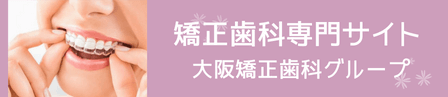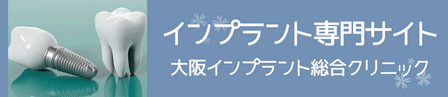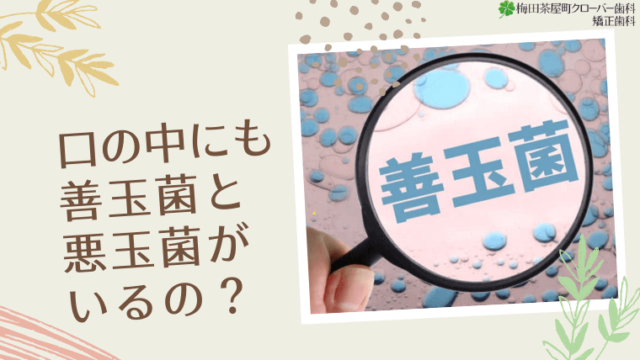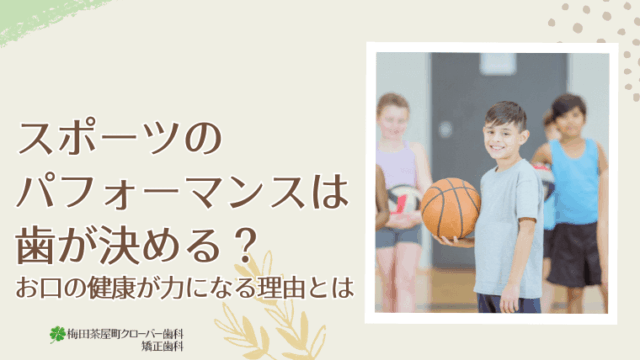歯のために避けた方がいい飲み物はありますか?

日常の飲み物選びが、“歯の健康”に大きく関わっていることをご存知ですか?
このページは、「歯のために避けた方がいい飲み物は?」と気になっている方や、虫歯や歯の黄ばみが気になる方へ向けて、歯科医師の視点から“飲み物と歯の関係”をやさしく解説します。
この記事はこんな方におすすめです
- 歯に悪い飲み物って何?と疑問に感じている方
- 子どもや家族の“飲み物習慣”を見直したい方
- 虫歯・酸蝕歯・着色のリスクを下げたい方
- 日頃からコーヒー、ジュース、炭酸飲料をよく飲む方
- 歯科医院で「飲み方やタイミング」について具体的なアドバイスが欲しい方
この記事を読むとわかること
- 歯に悪影響を及ぼしやすい具体的な飲み物とそのリスク
- 普段何気なく飲んでいるものと歯科的トラブルの因果関係
- 飲み方・タイミングの工夫や、日々のケアで“歯を守るコツ”
「今よりちょっと歯を大切にしたい」「家族にも知ってほしい」そんなあなたに役立つヒントを、わかりやすくお届けします。
歯のために避けた方がいい飲み物たち
飲食することで歯はダメージを受ける可能性があります。歯がダメージを受けると、お口の健康だけでなく、全身の健康にも深刻な影響を与えることがあります。
まず、歯に悪い影響を与える飲み物は、歯を溶かしてしまう「酸性」の飲み物と、虫歯菌のエサになりやすい「甘い」飲み物です。歯に悪いとされる飲み物についてご説明します。
1.炭酸飲料

炭酸飲料は酸を含む飲み物で、酸は歯のエナメル質を溶かしてしまいます。また、炭酸飲料は非常に多くの砂糖を含んでおり、お口の中の虫歯菌が糖を取り込んで酸を出し、歯にひどいダメージを与えます。
2.コーヒー

コーヒーには活性酸素を抑える作用があるため、身体に良いと言われる反面、コーヒーに含まれるステインは着色することで歯の表面を汚す可能性があります。
また、コーヒーは酸性の飲み物で、pH5程度です。pH6くらいから歯が溶け始めます。そのため、コーヒーが長い時間お口の中にとどまると歯の表面のエナメル質を溶かしていきます。
コーヒーに砂糖を入れなくても、頻繁に飲んでいれば、食べ物や飲み物に含まれる酸によって歯が溶ける酸蝕歯(さんしょくし)と呼ばれる状態になります。もちろん、コーヒーに砂糖を加えると、虫歯を引き起こすリスクが高まります。
3.アルコール

アルコール飲料は、糖分が原因でエナメル質をすり減らす可能性があります。アルコールが脱水状態になっているため、歯茎も苦しむ可能性があります。赤ワインのような飲み物も歯を汚す可能性があります。結論–アルコール消費量を最小限に抑えるようにしてください。
ビール、チューハイなどにも注意しましょう。
4.フルーツジュース

一般的に健康的と見なされるフルーツジュースでさえ歯のためには避けるべき飲み物に含まれます。炭酸飲料と同様に、フルーツジュースには大量の砂糖が含まれているため、エナメル質がすり減り、歯垢の蓄積が促進されます。
実際の診療でも、普段ジュースや炭酸飲料をよく飲んでいる方に、歯へのダメージが見られます。ご自身では健康的だと思っていたフルーツジュースも、意外と酸や糖分が多いことをご説明すると驚かれる方が多く、日常的な飲み物の選択が歯の健康に直結することを実感しています。
毎朝オレンジジュースを飲む習慣のある方は、コップ一杯の水と食後の歯磨きで洗い流してください。
歯に悪い飲み物の特徴は?
pH値が低い、つまり酸性の飲み物は、歯を溶かしてしまいますので、虫歯になりやすいです。pH(ペーハー、ピーエッチ)とは水素イオン濃度の略称のことで、液体が酸性かアルカリ性かを数値で示します。
数値は7がちょうど真ん中で「中性」を示し、7より小さいものは「酸性」、7より大きいものは「アルカリ性」に分類されます。酸性の飲料は歯を溶かしてしまいますので、虫歯を防ぐためにはpH7より低い酸性の飲み物は摂取を控えましょう。
実際に歯が溶け始めるpHは5.5程度といわれていますので、H5.5以下の飲み物には特に注意しましょう。
歯に悪い飲み物の特徴早見表
| 飲み物の特徴 | 歯への悪影響 | 具体例 | ワンポイント対策 |
|---|---|---|---|
| 糖分が多い | 歯垢が増えやすく、虫歯の原因に | ジュース、加糖コーヒーなど | 無糖の飲み物に切り替えたり、水でうがい |
| 酸性である | 歯の表面(エナメル質)が溶けやすい | 炭酸飲料、スポーツドリンク | 飲んだら30分以上空けて歯磨きをする |
| 色素が濃い | 歯の着色やくすみの原因になる | コーヒー、紅茶、赤ワイン | ストローで飲む、水で口をゆすぐ |
| 高温・低温すぎる | 歯に刺激を与え、知覚過敏を助長 | 熱いお茶、冷たいアイスコーヒー | 常温に近い温度で楽しむのがベスト |
| 長時間飲み続ける | 口内が酸性状態になりやすい | ペットボトル飲料のちびちび飲み | 時間を決めて飲む、すぐに水でリセット |
これらの飲み物による歯へのダメージは?
酸・糖・色素の組み合わせで歯はゆっくりと傷んでいく
一見無害に見える飲み物でも、毎日何気なく飲み続けることで、歯にじわじわとダメージが蓄積されていくことがあります。とくに、以下のような飲み物は複数の“歯に悪い要素”を兼ね備えているため、リスクが高まります。
代表的なダメージの例
| 飲み物の種類 | 含まれる成分 | 歯への主な影響 |
|---|---|---|
| 炭酸飲料(コーラなど) | 強い酸性・高糖分 | 酸蝕症・虫歯の進行 |
| スポーツドリンク | 酸性+糖分+長時間の摂取習慣 | エナメル質の脱灰・知覚過敏 |
| 加糖コーヒー・紅茶 | 糖分・色素 | 虫歯と着色のダブルリスク |
| フルーツジュース | 天然の糖+果実由来の酸 | 酸蝕症+糖分による虫歯リスク |
| エナジードリンク | 高糖分・カフェイン・酸性 | 酸蝕、虫歯、口腔内乾燥によるリスク増加 |
ダメージの蓄積は“気づかないうちに進行”するのが怖い
これらの飲み物は、一度に大量に飲むよりも、「毎日少しずつダラダラ飲む」ことの方がダメージが大きくなりがちです。飲むたびに口の中のpHが酸性に傾き、歯の表面の再石灰化が追いつかなくなるからです。
長年の臨床経験から言えることは、特に「だらだら飲み」をしやすい方は酸蝕歯や虫歯リスクが急激に高まる傾向があることです。炭酸飲料やスポーツドリンクなど、ペットボトルで長時間ちびちび飲むスタイルは、エナメル質を溶かす時間が延びるため要注意です。飲むなら一気に飲み終えて、その後は水やお茶でお口をゆすぐことをおすすめしています。
とくに以下の症状が出てきたら要注意!
- 歯がしみる(知覚過敏)
- 歯の先端が透明っぽくなってきた(脱灰)
- 着色が取れにくくなった(色素沈着)
- 虫歯の進行が早い
ポイントは“量”より“頻度と習慣”
「週1回コーラを飲む人」と「毎日少しずつ甘い飲み物を飲む人」では、後者の方が圧倒的にリスクが高いのが実情です。
出典:食品やサプリメントで歯が溶ける?酸蝕症をご存じですか?(国立健康・栄養研究所 食品保健機能研究センター)
これらの飲み物を飲んだときはどうする?
ものを食べたときには、歯と歯の間に食べ物が挟まったり、歯に歯垢がこびりついたりしますが、飲み物の場合は、歯の表面に残っているものは少ないと考えられます。
そこで、歯に悪い飲み物を飲んだときに虫歯にならないための方法は、まず水を飲んでお口の中を洗い流すことです。液体の洗口薬でうがいをすれば、なお良いです。
歯磨きやデンタルフロスを追加しても良いのですが、やり過ぎは禁物です。歯のセルフケアのやり過ぎで逆に歯を傷めないように注意しましょう。
歯のために避けた方がいい飲み物に関するQ&A
歯に悪い飲み物の特徴は、主に2つあります。第一に、pH値が低い「酸性」の飲み物です。これらの飲み物は歯を溶かしてしまい、虫歯のリスクを高めます。第二に、「甘い」飲み物も問題です。これらは虫歯菌のエサとなり、さらに歯を傷つけます。
炭酸飲料は酸を含み、歯のエナメル質を溶かしてしまいます。さらに、多くの炭酸飲料には砂糖が含まれており、虫歯菌がこれをエサにして酸を生成するため、歯にダメージを与えます。これらの理由から、炭酸飲料は歯に悪い影響を与える飲み物とされています。
アルコール飲料には糖分が含まれており、これがエナメル質をすり減らす原因となります。また、アルコールが脱水作用を持つため、歯茎も影響を受ける可能性があります。赤ワインなども歯を着色させる恐れがあります。アルコール消費量を控えることで、歯の健康を保つことが重要です。
まとめ

酸性の飲み物は歯を溶かしますが、だから飲んではいけないのではなく、飲み方に気をつけましょうということです。
酸性の飲み物をダラダラと長時間にわたって飲み続けると、お口の中が酸性に傾いた状態が続き、歯が溶かされ続けることになります。水を飲んだり洗口剤でお口をゆすぐなど、歯を溶かさないように工夫しましょう。