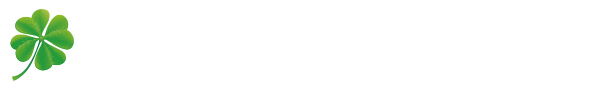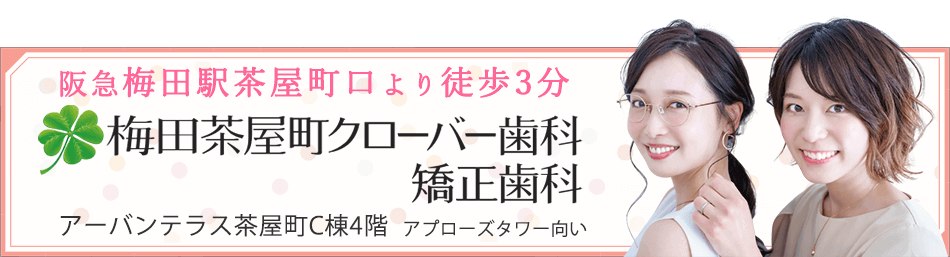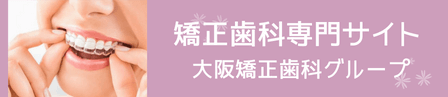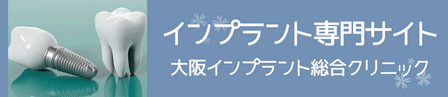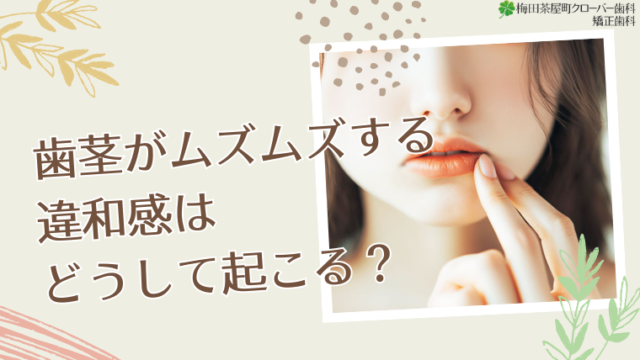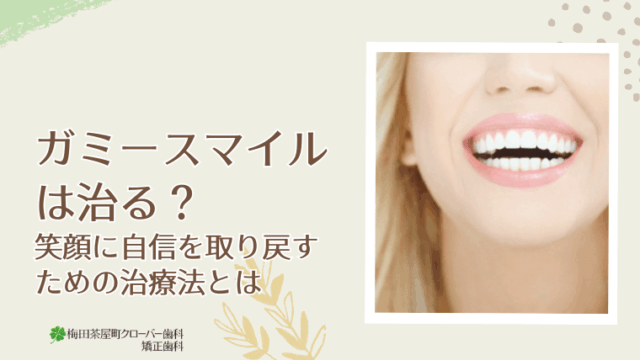歯ぎしり・食いしばりの多くの原因は、ストレスや噛み合わせ、生活習慣などに関係しています。
寝ている間やふとした瞬間に、歯をぎゅっと噛みしめていること、ありませんか?「無意識に歯ぎしりしていた」と指摘されて驚いた経験がある方も多いはず。これ、実は誰にでも起こりうる反応なんです。
この記事はこんな方に向いています
-
- 朝起きたときに顎がだるい・痛いと感じる方
- 寝ている間に歯ぎしりしていると言われた方
- 歯がすり減ってきたように感じている方
- 歯科医院で「歯ぎしりしてませんか?」と指摘された方
この記事を読むとわかること
- 歯ぎしり・食いしばりが起こる理由
- ストレスや噛み合わせとの関係性
- 起こるタイミングと種類の違い
- 放置するとどうなるか
- 予防と対策の具体的方法
目次
歯ぎしり・食いしばりは原因を理解しよう
歯ぎしり・食いしばりは多くの場合、無意識に行われています。そのため本人が自覚していないケースも少なくありません。これらのクセは歯や顎、筋肉に大きなダメージを与えるため、原因を知って適切に対処することが大切です。
無意識でも歯や顎に負担がかかるため、早めの対応が大切です。
原因はストレスや噛み合わせ、生活習慣などさまざま
歯ぎしり・食いしばりの主な原因は「精神的なストレス」に加えて、「噛み合わせのズレ」や「睡眠の質」、「日中の姿勢」などが関係しています。多くの要素が絡み合っているため、原因を1つに絞るのは難しい場合もあります。
ストレスや噛み合わせなど、複数の要素が原因となります。
主な原因
| 原因 | 説明 |
|---|---|
| ストレス | 緊張や不安によって筋肉がこわばり、無意識の歯ぎしりを引き起こすことがあります。 |
| 噛み合わせのズレ | 不正咬合によって、上下の歯がきちんと噛み合っていないと、無意識に力が入ります。 |
| 睡眠の質の低下 | 睡眠中にレム睡眠とノンレム睡眠がうまく切り替わらないと、歯ぎしりが起こりやすくなります。 |
| 日中の食いしばり | デスクワークや集中時に無意識で食いしばる癖がある人は要注意です。 |
このように、精神的・身体的な要因が複合的に影響するため、歯ぎしりや食いしばりを「癖」で片づけずに、根本の原因を見極めることが改善への第一歩です。
歯ぎしり・食いしばりの原因とその影響
| 主な原因 | 影響しやすい症状・トラブル |
|---|---|
| ストレス・緊張 | 無意識の噛みしめ、就寝中の歯ぎしり、筋肉のこわばり |
| 噛み合わせのズレ(不正咬合) | 歯の偏った摩耗、顎関節への過剰な負担、口の開閉の違和感 |
| 睡眠の質の低下 | 睡眠中の歯ぎしり増加、日中の倦怠感、朝の顎の疲れ |
| 長時間の集中(パソコン作業など) | 起きている時の食いしばり、顎関節の緊張、首や肩のコリ |
| 過去の治療物の不適合 | 被せ物や詰め物の破損、特定の歯への負担集中、歯の違和感 |
ストレスと自律神経の関係から見た“歯ぎしり・食いしばり”
ストレスが歯ぎしりや食いしばりに影響する背景には、自律神経の乱れが関係しています。特に交感神経が優位になっていると、筋肉がこわばり、無意識に顎に力が入る状態が続いてしまうのです。
ストレスは自律神経を通して、噛みしめの癖を引き起こします。
現代人は仕事・家事・人間関係などで慢性的にストレスを感じやすく、自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスが乱れやすくなっています。特に寝ているときは、脳は休んでいても身体は「緊張モード」になってしまいがち。その結果、歯ぎしりが起こることがあるのです。
対策のヒント
- 就寝前のスマホやPCを控える
- 寝る前に深呼吸やストレッチをする
- カフェインやアルコールを控える
- リラックスできる音楽を流す
ストレスマネジメントと自律神経ケアは、噛みしめ予防の大切な第一歩。心と身体のケアは、歯の健康にもつながっています。
噛み合わせ(不正咬合)と歯ぎしりの密接な関係
歯ぎしりや食いしばりは、噛み合わせのズレが引き金となることもあります。不正咬合のある方は、無意識に「正しい位置に戻そう」として顎に力が入ってしまうことがあります。
噛み合わせのズレが、歯ぎしり・食いしばりを引き起こす原因になることがあります。
上下の歯の当たり方が偏っていたり、歯並びがガタガタしていたりすると、噛むときの力がうまく分散されません。その結果、一部の歯に負担が集中し、無意識に調整しようとする動きが「歯ぎしり」となって現れるのです。
こんな人は要注意
- 歯並びが悪く、左右どちらかでしか噛めない
- 昔に治療した被せ物や詰め物が合っていない
- 顎のズレを感じる
- 口を開けると音が鳴る・引っかかる
不正咬合を放置すると、歯ぎしり・食いしばりが悪化する可能性もあります。気になる症状があれば、歯科医院で噛み合わせのチェックを受けましょう。
起こるタイミングや種類も人によって異なる
歯ぎしりと食いしばりは「起きているとき」と「寝ているとき」で特徴が異なります。どのタイミングで起こっているかを知ることで、対策の方向性も変わってきます。
起きているとき・寝ているときでタイプが異なります。
種類と特徴
- 睡眠時ブラキシズム(歯ぎしり)
・音を立ててギリギリと歯をこすり合わせる
・家族に指摘されて気づくことが多い - 覚醒時ブラキシズム(食いしばり)
・パソコン作業中や運転中に起こりやすい
・歯を当て続けていたり、ギュッと噛みしめる
どちらも歯や顎にダメージを与える可能性があるため、ライフスタイルや仕事の内容も含めて観察し、自分の癖を知ることが重要です。
放っておくと歯や顎に大きな負担がかかる
歯ぎしり・食いしばりをそのままにしていると、歯がすり減る、被せ物や詰め物が割れる、顎関節症になるなど、多くのトラブルにつながります。
放置すると歯や顎にさまざまな悪影響が出ます。
歯や顎への主な影響
- 歯のすり減り・欠け
- 被せ物・詰め物の破損
- 顎関節の痛み・開口障害
- 歯周病の悪化
- 頭痛や肩こり
歯ぎしり・食いしばりを軽く見ずに、予防と早期対処を心がけることで、歯の健康を守ることができます。
家族ができるサポート:歯ぎしりを「気づかせる」ことが第一歩
本人が無自覚なことが多い歯ぎしりや食いしばり。身近な人が「音」や「様子」に気づいて声をかけることで、早期発見・対策につながります。
家族の気づきと声かけが大きな助けになります。
サポートのポイント
- 寝ているときにギリギリという音がする場合は、やさしく伝える
- 朝起きたときに顎のだるさを聞いてみる
- デスクワーク中に無意識に噛んでいるようなら、指摘してあげる
- 「気にしすぎないでね」と安心させる声かけが大切
「また歯ぎしりしてたよ!」と責めるのではなく、「もしかしたら無意識に力が入ってるかも?」とやさしく気づかせる姿勢がポイント。歯ぎしりはデリケートな悩みだからこそ、周囲の協力がとても大切です。
マウスピースやストレスケアなどで予防・改善
就寝時に装着する「ナイトガード(マウスピース)」の使用や、噛みしめに気づくための意識づけ、ストレス管理、歯科での噛み合わせの調整などが予防・対策として有効です。
生活習慣の見直しやマウスピースで対策が可能です。
おすすめの対策
- マウスピースの装着
→ 就寝時に歯を保護するナイトガードを使うことで、歯のすり減りや顎への負担を軽減します。 - 姿勢と噛みしめの意識
→ 「歯と歯は当たっていないのが正常」と意識して、リラックスした口元を保ちましょう。 - ストレスの軽減
→ 睡眠の質を高めたり、リラクゼーションや運動を取り入れることが大切です。 - 歯科医院での相談・調整
→ 不正咬合がある場合、かみ合わせを見直すことで改善されるケースもあります。
原因に合わせて複数の対策を組み合わせることで、歯ぎしり・食いしばりの改善が期待できます。自己判断せず、歯科医院での相談もおすすめです。
歯ぎしり・食いしばりに関するQ&A
条件によっては保険が適用されます。診断名が「歯ぎしり(ブラキシズム)」と認められた場合、ナイトガード(就寝時用のマウスピース)が保険適用になることがあります。詳しくは歯科医院で相談してみましょう。
歯ぎしりは主に就寝中に「ギリギリ」と歯をこすり合わせる動き、食いしばりは日中・夜間問わず「グッと噛みしめる」無意識の力の入れ方を指します。どちらも歯や顎にダメージを与える可能性があります。
子どもの歯ぎしりは一時的な場合が多く、成長とともに自然に治るケースもありますが、長期間続く・歯がすり減っているなどの症状があれば、歯科医院で相談するのがおすすめです。
生活習慣の見直しやストレスの軽減、就寝前のリラックス習慣の導入などで改善が期待できますが、無意識で行っている場合は歯科医院でのマウスピースの使用や噛み合わせ調整が効果的です。
歯のすり減り・ヒビ・被せ物の破損・顎関節症など、さまざまなトラブルにつながります。早めの対策で歯の寿命を守ることが大切です。
まとめ
歯ぎしり・食いしばりは、「クセだから」と軽視せず、原因を理解し、生活習慣や噛み合わせを見直すことが大切です。自分では気づきにくい症状だからこそ、歯科医院での定期的な健診や、必要に応じたマウスピースの使用で、歯と顎を守りましょう。